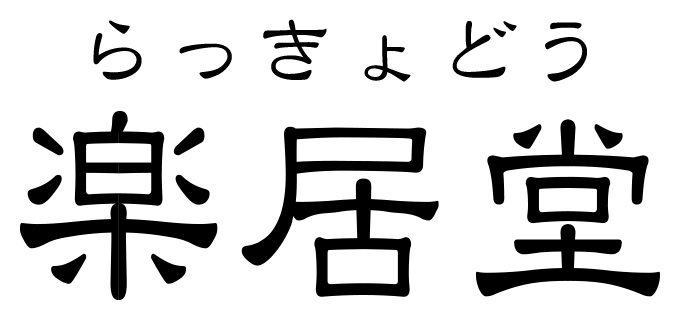~心配性って、実は“体質”かもしれません~
「いつも先のことが気になってしまう」「夜になると不安が押し寄せてくる」——そんな“心配しすぎる”傾向、実は心だけの問題ではなく、身体の状態とも深く関係しています。
心配性の人ほど胃腸が弱かったり、眠れなかったり、肩こりがひどかったりすることは、自分や周りを見ていてもわかりますよね。
心配しすぎることが、身体の不調につながり、逆もまた真なりで、体調の不調がメンタルに影響していることもありますよね。
☘心配性の人がなりやすい不調
・胃腸の不調
・睡眠の質が低下
・肩こり・頭痛
・動悸・息切れ
・皮膚トラブル
ストレスの影響で持続的に緊張が高まると、まず筋肉が強張り、自律神経のバランスがうまくいかず、さらには免疫力が低下してしまう。結果として上記のような不調が出やすくなってしまうのですね。
☘東洋医学では?(思いは脾をやぶる)
東洋医学では、心配や思い悩む感情は「脾」に影響を与えるとされます。脾は消化吸収だけでなく、気・血を作り出す重要な臓腑。過度な思慮は脾を傷め、結果として「気虚」「血虚」「湿滞」などの症状が現れます。だるい・やる気が出ない・寝ても疲れが取れないといった症状です。
また、心配が長期化すると「心」にも影響し、睡眠障害や動悸などの“神志”の乱れが起こると考えられています。
昔の人は「思い悩むとお腹が弱る」と言っていました。まさに、心配しすぎることで“気のめぐり”が悪くなり、体のあちこちに不調が出てくるという考え方です。
☘心配しすぎる人のためのおすすめのツボ
・掌の真中(労宮) 手をグーにしたときに中指が当たるところ 気持ちをほぐす
・手首の内側(大陵) 手首のしわの真ん中 気持ちを落ち着かせる
・かかとの真ん中(失眠) 足の裏のかかとの真ん中 寝つきが良くなる
どのツボも強く押してはいけません。深くゆっくりとした呼吸をしながら、皮膚の表面に刺激が入ればOKです。 もしも時間的に余裕があるようでしたら、失眠のツボは温めると効果があります。(お灸でもホッカイロでも)
☘心配しすぎる方へ
心配性は、性格だけでなく「身体のサイン」かもしれません。胃腸の不調や眠れない夜が続いているなら、まずは身体をゆるめてあげることが大切です。
ツボ押しや深呼吸、そしてちょっとした生活の見直しで、心も身体も少しずつ軽くなっていきます。「心配しすぎる自分」を責めるのではなく、やさしくケアしてあげましょう。